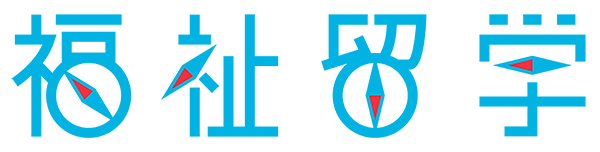社会福祉士の資格取得を目指し福祉の勉強に励んでいるKさん。「その土地と支援内容がどう繋がっているのか」という点を学び見識を広げていきたいと、5日間の福祉留学へ。
長野県富士見町の連携施設「社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会(以下、富士見町社会福祉協議会)」(現在は留学先ではありません)での経験をお聞きしました。
福祉留学参加のきっかけや動機を教えてください!
地域特性に応じた福祉支援の実際に興味があり、その現場を見てみたいと思ったからです。
学内で行った社会福祉士実習では、他市の社会福祉協議会に伺い、社協の持つ「自ら足を運んでニーズを見つけられる」という特徴に興味を持ちました。また、地域によって展開するサービスや内容も大きく異なることを知り、他の社協の取り組みも見てみたいと考えていた際にこの福祉留学を見つけ、「これは!」と思い応募しました。
富士見町社会福祉協議会は訪問介護や定期巡回等、ご高齢の方に向けたサービスを始め多様な事業を展開されているとのことで、ニーズと支援の関係性についても広い視点で学べると思い、参加を決めました。
福祉留学先である長野県の印象はいかがでしたか?
自然が豊かで、ゆったりとした印象でした。町民の方々はとても優しく、アットホームな雰囲気がとても心地良かったです。
私が伺った期間は偶然にも雪。天候に左右されてしまった部分もありましたが、一面の雪景色を見れたことは思い出のひとつとなりました。
また、地域交流、世代間交流ができる場所やイベントが多く、活発に行われているという印象を受けました。
町民の方々の繋がりや温かさは、こうした交流の場から生まれている部分にある「思い」、「町」や「人」、「支援」について多角的に学べたことがとても嬉しかったです。


留学先施設である富士見町で、印象に残った体験やエピソードがあれば教えてください!
「だれでも食堂」のオープニングに参加させていただいたことが特に印象に残っています。
既存の取り組みである子ども食堂を更にパワーアップさせ、「誰でも食べに来られるように」との願いを込めたものだそう。
事業に携わる社協や役場の方、料理を作ってくださる方、そして実際に食べに来られた方々それぞれにお話を伺うことができ、地域のことについて理解を深められた時間でした。
また、大学や社会福祉士実習では地域における集いの場、コミュニティの存在意義について考える機会が多かったため、富士見町ならではの実践の場に参加させていただいたことでその必要性や効果をより実感できたと思っています。
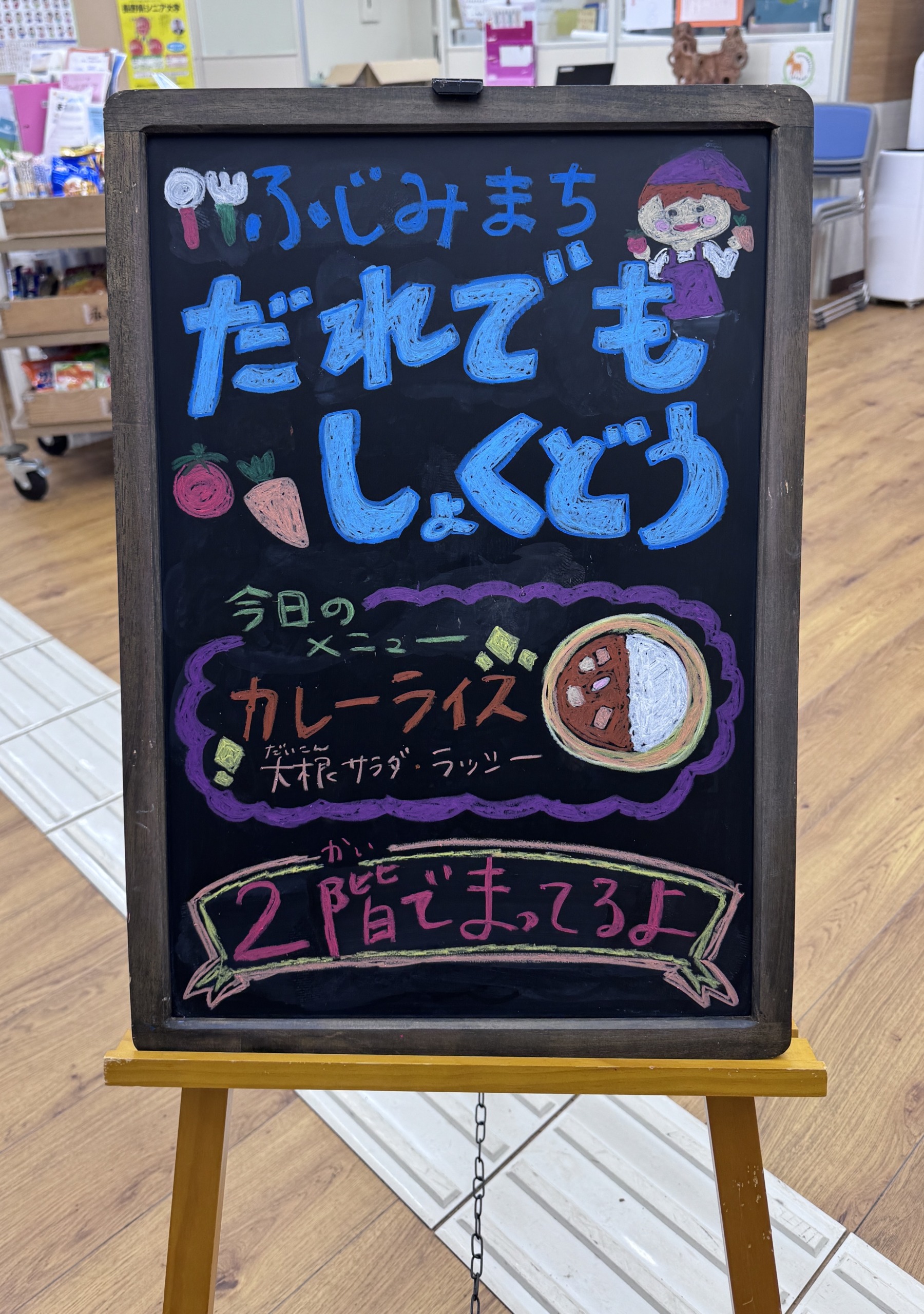
福祉留学に行く前と後で変化したことはありますか?
訪問事業は「外出が難しい方に対する支援」という漠然としたイメージでしたが、複数の訪問に同行させていただき、それぞれの方に対する支援の方法、声掛けは本人の意思を第一に考えることが重要だと理解できました。
以降は「利用者の生活リズムやできることを阻害せず、強みを伸ばせる支援を展開している」という見方に変わり、長年住んでいる方が多いからこそ、その土地における生活、今まで通りの生活を継続することは、地域生活の安定や安心感に繋がると学びました。
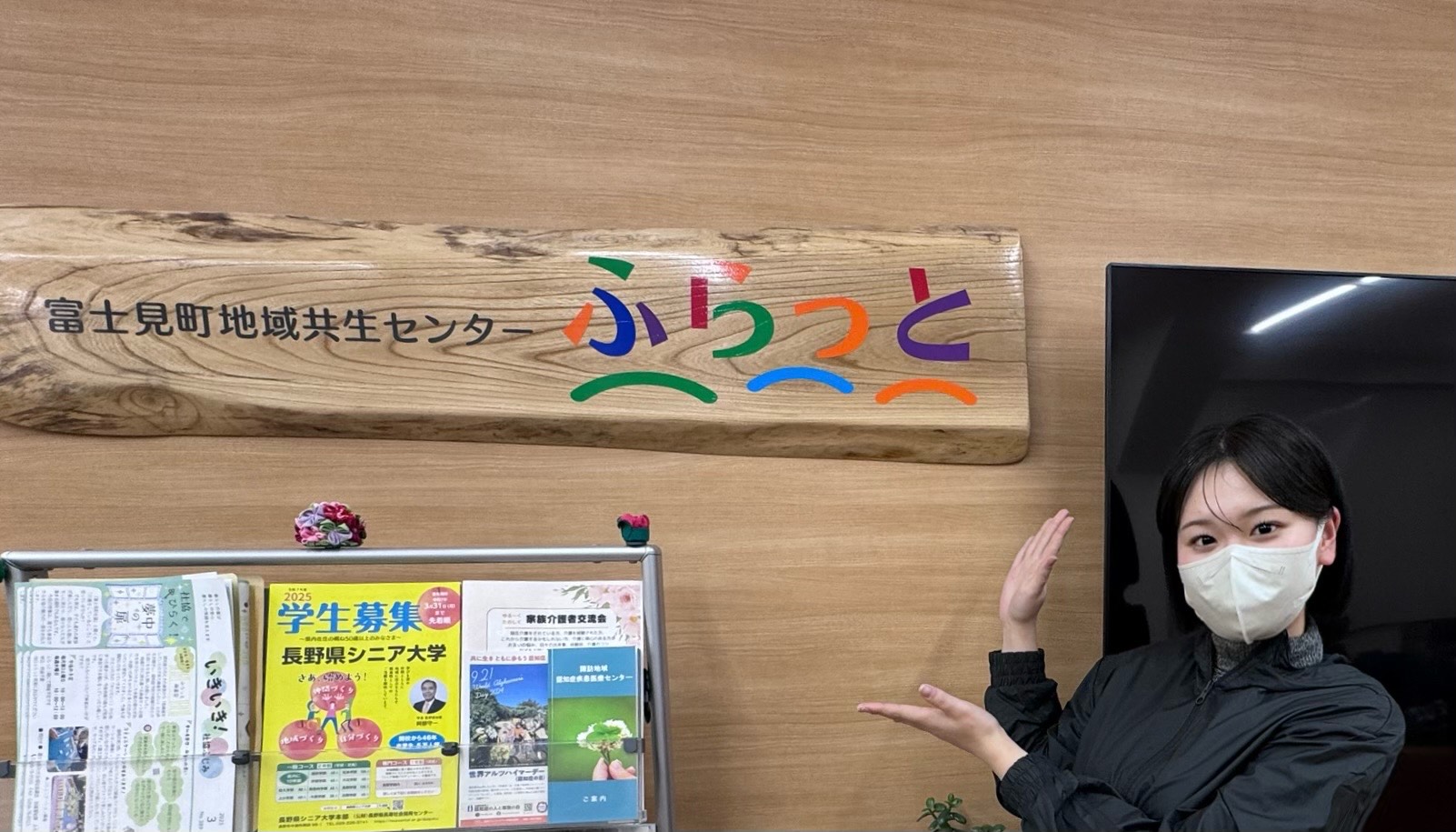
次に福祉留学へ行く人たちへメッセージをお願いします。
心配性な私は「1人で大丈夫かな?やっていけるかな?」と不安で、チャレンジすることをためらっていました。
しかし、その勇気を振り絞ってみた後にはとても素敵な経験が待っていました。
利用者の方と交流し、職員の方からお話を伺い、地域とのつながりを知る、机上では学べない体験を沢山することができると思います。
自分の知見を広げるためにも、福祉を学ぶ上でも、すごくすごくおすすめです^ ^