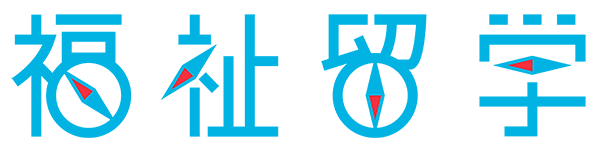横浜市立大学医学部の印南麻央さん。
「実習ではなかなか見られない地域連携を見てみたい」と学校の春休みを利用して、5日間の福祉留学へ。
福井県福井市の連携施設「オレンジキッズケアラボ」(以下略、ケアラボ)での経験をお聞きしました。
福祉留学参加のきっかけや動機を教えてください!
私の専攻は医学ですが、将来は医療・介護・福祉をつないで問題解決ができるようになりたいという想いがあり、学生のうちにどのような連携がされているのか知りたいと考えていました。
また、「病院の中だけではなく、人々の生活の中での医療・福祉がどのような形で実践されているか見てみたい」と考え、暮らしに開かれた医療やまちづくりを行っているオレンジキッズケアラボに福祉留学をしようと決めました。
福祉留学先である福井市の印象はいかがでしたか?
福井市は都市と自然のバランスがちょうどよいまちだと感じました。
自然を楽しみつつも、生活する上での不便さはなく、周囲のお店も充実していました。
海鮮・ソースカツ丼・おろしそばなど、福井ならではの食を満喫することができました。
また、行った時期はちょうど桜が満開だったので、ケアラボの子どもたちと一緒に近くのお城にお花見に行ったり、行き帰りの道で桜を見たりと春ならではの楽しみ方が出来ました。

留学先施設であるオレンジキッズケアラボで、印象に残った体験やエピソードがあれば教えてください!
5日間で多くの方とお話しする機会がありました。
医療的ケアが必要な子どもたちとの関わりだけでなく、関連施設のクリニックの訪問診療に同行させていただいたり、併設されているカフェで働いている方にお話を伺ったり、社会福祉士やコミュニティナースの方とお話ししたりと、様々な視点から地域に開かれた医療・福祉のあり方や連携について知ることが出来ました。
それぞれの人の想いに触れ、自分自身の将来のキャリア選択や生き方を見つめなおすきっかけにもなりました。
子どもたちとの関わりでは、最初はどう接したらよいか戸惑った時期もありました。ですが、「相手が発するサインをどう受け取っていくか」というコミュニケーションの本質は障害の有無にかかわらず同じである、と気づくことが出来ました。
施設内での子どもたちとの関わりというミクロな視点と、施設間や地域を巻き込んだ連携というマクロな視点をどちらも経験できたことで、医療や福祉をとりまく全体像を把握するヒントが得られたと感じています。

福祉留学に行く前と後で変化したことはありますか?
自分の中にあった「こうあるべき」という前提がどんどんなくなっていくのを感じました。
就学支援のお話を聞いたり、ケアラボで子どもたちと関わっていく中で、どんなことに対しても「できない」と切り捨てるのではなく、「どうしたらできるか」をできるだけフラットな状態で一緒に考え、実践していくこと。それが大きく選択肢が広がっていくと実感しました。
また、訪問診療の現場を見ることで、病院の中だけではなく地域での生活に根ざした医療という視点を意識できるようになりました。今後、この視点を意識していきたいと思っています。
次に福祉留学へ行く人たちへメッセージをお願いします。
直接福祉に関わっている人も、そうでない人にもぜひ行ってみてほしいです。
コーディネーターさんも受け入れ先のスタッフさんも、皆さんの学びたいこと、現在の仕事・専攻などに応じて柔軟に機会を設定してくださいます。
また、福祉留学中の目標を設定すると、さらに学びが深められると思います。
福祉留学で得たことを帰ってきてからの生活にどう活かすか?を意識してみると、より充実した福祉留学の日々を送れるのではないかと思います!