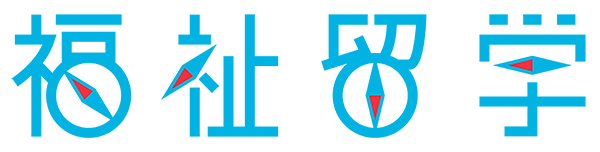小学校教員を目指している広島大学教育学部の四方さん。一週間の福祉留学へ。
徳島県三好市市の連携施設「社会福祉法人池田博愛会(以下、池田博愛会)」での経験をお聞きしました。
福祉留学参加のきっかけや動機を教えてください!
福祉留学自体は、大学の先生からの紹介で知りました。
当時、特別支援学校の教師になるか、教師以外の職業で障害に関わる仕事に就くかということを悩んでおり、他の様々な職業の方(医療や福祉関係の方等)の働いている様子を知りたいと思っていた事が応募のきっかけです。
また、教師になるにあたっても、就労の現場の様子や医療的ケア児の様子について知っておくことで、教師になった際に、自分の担当する児童生徒がどのような将来を歩んでいきそうかなという見通しや、どういう自立活動をしていった方が良いのかな、ということを考えやすくなると思ったためです。
自分自身の今後のキャリアを見据え、少しでも現場について知っておきたいという思いもありました。

福祉留学先である徳島県の印象はいかがでしたか?
人のあたたかさを実感できる地域、だと感じました。夏祭りや地域交流拠点となる場所で、福祉留学先でお話しした利用者さんやお世話になった方などに会ってお話しすることができました。
1週間という短い期間でしたが、近くに知っている人がいる、という安心感をもつことができました。人と人とのつながりが強い地域というものをはじめて実感しました。また、同世代(20代)の方たちが、地域を盛り上げるためのイベントを開催しているという話を聞きました。
地域のための行動力と愛を感じて、魅力的な地域だということが伝わってきました。

留学先施設である池田博愛会で、印象に残った体験やエピソードがあれば教えてください!
発達支援の施設では、子どもたちが就学時になるべく困らないように、小学校からの学習が定着するための養育を行っていることを学びました。しかし小学校では、発達支援センターを利用していた子どもは授業中も席に座ることができているから、などと個に合った指導や支援を受けることができないというお話を聞きました。
小学校教員として、子どもの養育歴や得意なこと、今の課題などを把握することが大切だと感じました。
現在の実態だけではなく、それまでの育ちや養育について知ることで、効果的な支援を考えることにつながることを、福祉の視点から考えることができました。

福祉留学に行く前と後で変化したことはありますか?
福祉留学を通して、私自身が今後関わる子どもたちが、義務教育修了後の社会生活を送るために必要な力は何かを考えることができました。
今まで私は、子どもたちが「自立」して生きるために育みたい力、について考えていました。しかし、障害がある方々の実際の社会生活について知っていることが少なく、想像するだけでは難しいことがありました。
今回福祉留学にて障害のある方々が働く事業所やグループホームでの暮らしについて見聞きし、学校教育で伸ばしておきたい力を具体的に考えることができるようになりました。

福祉留学は、地域福祉を間近で見て体験しながら、自分の実感として経験が残るのがとても魅力的だと感じました。
私自身は教育の視点から福祉について学びましたが、自分の知りたいことや学びたいことを中心として、たくさんのことを見て聞いて体験してほしいです!
また、どの施設でもとても優しくたくさんのことを教えていただき、安心して体験ができました。
利用者さんとの会話の中から学ぶことや知ることがたくさんあったので、人とのつながりを感じながら福祉留学を楽しんでほしいです!