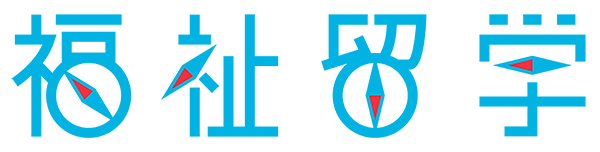特別支援教育や小学校教育について大学で学んでいる竹井さん。5日間の福祉留学へ。
長崎県佐世保市の連携施設「社会福祉法人 宮共生会(以下、宮共生会)」での経験をお聞きしました。
福祉留学参加のきっかけや動機を教えてください!
福祉留学自体は、大学の先生からの紹介で知りました。
当時、特別支援学校の教師になるか、教師以外の職業で障害に関わる仕事に就くかということを悩んでおり、他の様々な職業の方(医療や福祉関係の方等)の働いている様子を知りたいと思っていた事が応募のきっかけです。
また、教師になるにあたっても、就労の現場の様子や医療的ケア児の様子について知っておくことで、教師になった際に、自分の担当する児童生徒がどのような将来を歩んでいきそうかなという見通しや、どういう自立活動をしていった方が良いのかな、ということを考えやすくなると思ったためです。

福祉留学先である佐世保市の印象はいかがでしたか?
私は、留学先のグループホームが満室であったらしく、急遽佐世保市にあるホテルに滞在したのですが、初日にはホテルから非常に大きい海が見えたりして、その景観にとても驚きました。
また、近くに「五番街」というデパートのような場所があり、せっかく長崎に来たならちゃんぽんを食べておこうと決めていたので、ちゃんぽんを食べました。本当においしかったです!
地域の方々と関わる機会は中々なかったのですが、ホテルのフロントさんやお店の店員さん、皆さんすごく優しかったです!

留学先施設である宮共生会で、印象に残った体験やエピソードがあれば教えてください!
私は生活介護・放課後等デイサービス・就労支援・相談支援といった様々な施設を見学させていただきました。
どの施設でも印象に残ったことがあるのですが、どれか一つ選ぶなら、重度の障害があり、発声が困難な方々の「まなざし」です。
様々な施設で、重度の障害があり、発声することが難しい方とお会いしたのですが、どの方も、スタッフさんに用がある時、何か言いたいことがある時に、じぃーとスタッフさんの方を見たり、歩行できる方は手をつかんだりしていて、この方たちは、声での意思疎通ができなくても、目で訴えて意思疎通を図ろうとしているのだなと思うとともに、その方たちの「まなざし」に込められた思いは何かということを推測できるようにしたいと思いました。

福祉留学に行く前と後で変化したことはありますか?
変化したことも本当に数多くあるのですが、福祉留学に行く前は、細かい作業ができる人であれば就労施設で働くことができるだろうと思っていました。しかし実際は、ただ作業や身の回りのことができていれば誰でも就労することができるというわけではないのだなと就労支援や生活介護の場を見て感じました。
また相談支援の現場で、就労A型とB型の違いについても学びました。A型は人数が決まっており、そもそもの求人が少ないため、A型での就労は難しいということを知ることができました。
就労については、まだ大学での講義でも深くは触れられていなかったため、特に学びになり、就労への難しさについて意識が変化しました。
次に福祉留学へ行く人たちへメッセージをお願いします。
迷っているなら行ってみた方が良いと思います!
私は1週間行き、毎日ハードスケジュールだったのですが、1週間あっという間で、本当に様々な体験・学びがありました。
私は大学で特別支援教育について学んでいるのですが、教育の場では中々学べない、学校を卒業した後の子どもたちの実際の生活について学ぶことができました。
このように、大学生の場合は普段専門で学んでいる分野と関連していたり、つながっていたりすることを深く学ぶことができると思います!